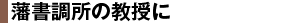
こうして名声があがった幸民には地位があとからついてきた。安政三年(1856年)には、幕府が設立した蕃書調所という洋学所の教授手伝に任命され、二年後には教授職に昇進した。名実ともに日本最高の洋学者の地位にのぼりつめたわけである。

島津斉彬
その翌年、幸民は島津斉彬の下で仕事をしたいとの希望をもって薩摩藩に籍を移し、その近代化事業(集成館事業)に技術面で協力した。しかし不運にも斉彬が急死したため、ふたたび江戸にもどることになった。
このころ大老井伊直弼による安政の大獄が起こるなど、世相は殺伐とし、また攘夷思想は洋学者を敵対視、幸民の身辺にも危険がおよんできた。それまで政治的な発言は控えてきた幸民だったが、政治に関心がなかったわけではない。仕事柄海外の情報には誰より精通していたし、持ち前の透徹した理性と判断力によって、日本の行く末を正確に見抜いていた。それがわかるのが福岡黒田藩の武谷椋亭(りょうてい)に宛てた書簡である。
この中で幸民は、旧弊な政治を改革するために九州の雄藩が団結し、西国の力をあわせて、政府の悪習を改革しない限り、庶民の苦しみを救う方法はないと書いている。さらに次の将軍候補として名があがっている一橋慶喜をその器ではないと批判している。
当時の情勢下、幕臣による幕府批判は、よほどの覚悟がなければできなかった。幸民の危機感がそれほど強かったということだろう。
晩年の幸民に関して特筆すべきは、英語への取り組みである。今や世界を制しつつあるのは英米であり、これからは英語に時代になると考えた幸民は、早くから英語を独力で学んでいた。大政奉還後の慶応四年(明治元年、1868年)、ここが潮時と見切りをつけた幸民は帰郷し、子息清一とともに英語と物理化学をおしえる塾を開いた。彼の名声をしたう入塾希望者は全国から殺到したが、開講からまもなく清一が維新政府から出仕を求められて上京することになり、幸民も同行した。しかしその翌年、病を患い、闘病ののち自宅で死去した。享年六十一才。西洋科学の研究紹介とその実験応用に捧げた生涯だった。
師信道の養子坪井信良は、幸民の人柄を、「清廉潔白で一本気で、信念をもって物事にあたる。その言葉は信頼のおけるもので、言い出したことは必ず実行する。交わりは広くないが、いったん親しくなれば長く、温かいつきあいを保つ」と記している。
幾多の困難を乗り越えて、医学や科学技術の探求を貫いた信念の人幸民は、また家族や友を愛し、郷土を愛し、藩を愛し、日本を愛した愛の人でもあった。その花も実もある生涯は、学問の探求と人間的な情愛とが決して矛盾しないことおしえてくれているようだ。
![]()
|