銀色に冷たく光るアルミの液体
 約35分後に鍋底のアルミ塊が溶け始めた。上辺のアルミ塊が音もなくゆっくりと沈み込んで行くと思ったら、下から液状のアルミがじわああ…と浮かび上がってくるのだった。その溶けたアルミニウムの表面が、村民の目を驚かせた。銀色に冷たく光っているのだ。思わず手ですくってみたくなるほどに冷たい色なのである。しかし、温度は660度以上、飛沫一滴が触れただけで、ジュッと皮膚を溶かし穴が空くのだ。危険なものは美しく魅惑的である。中西が、その美しさを、
約35分後に鍋底のアルミ塊が溶け始めた。上辺のアルミ塊が音もなくゆっくりと沈み込んで行くと思ったら、下から液状のアルミがじわああ…と浮かび上がってくるのだった。その溶けたアルミニウムの表面が、村民の目を驚かせた。銀色に冷たく光っているのだ。思わず手ですくってみたくなるほどに冷たい色なのである。しかし、温度は660度以上、飛沫一滴が触れただけで、ジュッと皮膚を溶かし穴が空くのだ。危険なものは美しく魅惑的である。中西が、その美しさを、
「おいしそう…」
と表現した。シュールで怖い。山の緑の水辺という場所だからこそ、非日常の物質の美しさがとりわけ目立つのだと思われる。室内実験ならば、そうでもなかったかもしれない。そして、科学の実験過程は危険な非日常。作り上げた物を我々は日常で便利に使うのである。失敗を繰り返し、命をも落としたであろう科学の先人たちに対して、村民は敬虔の念を捧げつつ、アルミを溶かし続けた。
必要量のアルミ溶解を完了。
アルミをタライで回転させる
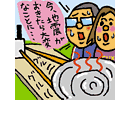 水平に設置されたロクロの上に乗せた直径50cmのタライに、溶けたアルミを移す。飛沫を飛ばさないように慎重に作業を進めた。プレ実験で適度と主任西脇が独断決定した回転速度40で、ロクロを回す(40とは変圧器の目盛り)。ほんとに速度40でいいんだな? と、村長湯本が何度も確認した。もしも失敗した場合、全責任を主任に負わせるための言質取りかもしれない。部下は辛いのだ。西脇の頬がこわばった。遠心力で液状のアルミはタライの外縁に振られ、中心が沈み込み始めた。そのまま、すなわち凹面を維持したまま静かに時間をかけてアルミは、自然冷却されつつ固まって行くのだった。タライに振動を与えないよう、息をのみながら一同でそっと見守る。
「今、ここで地震が発生したら、どうします?」
水平に設置されたロクロの上に乗せた直径50cmのタライに、溶けたアルミを移す。飛沫を飛ばさないように慎重に作業を進めた。プレ実験で適度と主任西脇が独断決定した回転速度40で、ロクロを回す(40とは変圧器の目盛り)。ほんとに速度40でいいんだな? と、村長湯本が何度も確認した。もしも失敗した場合、全責任を主任に負わせるための言質取りかもしれない。部下は辛いのだ。西脇の頬がこわばった。遠心力で液状のアルミはタライの外縁に振られ、中心が沈み込み始めた。そのまま、すなわち凹面を維持したまま静かに時間をかけてアルミは、自然冷却されつつ固まって行くのだった。タライに振動を与えないよう、息をのみながら一同でそっと見守る。
「今、ここで地震が発生したら、どうします?」
回転するロクロを見つめながら、加藤が呟いた。隣にいた原田が答えた。
「逃げるしかないでしょうね」
が、しかし、原田の目は、ロクロを担いで逃げるぞオレは、という決意の色を発していたのである。責任者である村の役員3名には、そこまでの決意はなかったのではなかろうか…。フセインも国民を置いて、さっさと逃げたからな。
1時間後に、地震および突風の被害もなくアルミの凹面鏡が出来上がった。しかしその表面は、予想されたとおり、ところどころに凹凸があり、しかも無数の傷のような穴が空いてしまった。金子助役と主任西脇の苦渋を、暮れかけた薄闇が隠している。
「この大きな凹面のアルミ鍋を火にかけて、ヤキトリを焼くのですね?」
そう言ったのは加藤である。違うでしょうよッ! と湯本は気色ばみかけたが、思わず爆笑。それが村民全員に広がり、笑いで実験初日を終えた。