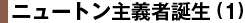
『求力法論』は、カイルがニュートン的化学の建設をめざしたものだった。その発想のもとは光は微粒子からなるというニュートンの『光学』にあった。化学、電磁気、生体などの諸現象を、粒子間に働く力で統一的に説明しようとするその試みは野心的なものだった。だが、なにぶん時代が早すぎた。
当時は原子や微粒子に基づく化学はまだ仮説の段階にあった。その実現は19世紀にドールトンが粒子ごとの質的な差異に基づいて、原子論的化学を確立するまで待たなければならなかった。
忠雄による『求力法論』の翻訳は最初から困難に直面した。
忠雄の語学力にはなんの問題もなかった。
彼の語学力は、長崎通詞の中でも傑出したものだった。その実力はオランダ語の文法を徹底的に研究し、品詞の概念や動詞の時制などを明らかにし、文法用語を確立したことからもわかる。
その忠雄をして翻訳に困難をきたした理由は、カイルの著作がもともと難解だったこともあった。だがそれ以上に大きかったのが、思想的な伝統や背景の差だった。
前述のように、『求力法論』の基礎となったニュートンの『光学』には、固体である粒子と、その間に働く力の概念が基礎にあった。しかし当時の日本にはそもそも粒子的な発想も、力学的な概念もなかった。西洋近代科学の根幹にある機械論的な自然観も見あたらなかった。つまりニュートンの科学思想に相当する考えがまったく存在しなかったのである。
|