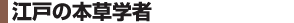
宝暦6年(1756年)故郷を立った源内は、大阪に立ち寄ったあと江戸に上った。江戸では本草学の大家、田村藍水の門をたたいた。
ここでめきめき頭角をあらわした源内は、生来のアイデアマンの本領を発揮し始めた。そのひとつが薬物の交換会「薬品会」の開催である。
第1回の開催は宝暦7年(1757年)で、会主は師の藍水が務めたが、実質的に取り仕切ったのは源内だった。第3回からは自ら会主となり、会はますます隆盛した。同時に本草学者源内の評判もあがった。
従来、この手の交換会は一門の枠にとらわれ、規模も小さかった。これに対して源内の提案した交換会は全国に物産を求め、参加の自由度も高いものだった。
江戸での評判を聞き及んだ頼恭公は、源内を再度召し抱え、待遇も引き上げた。同時に相模湾や紀州海岸での貝の採集を命じた。
しかしやはり異能の人源内は藩の枠にはとどまれなかった。宝暦11年(1761年)、彼は再び辞職を願い出た。このたびも聞き届けられたが、藩からは「仕官御構」という厳しい条件がつけられた。これは他藩への仕官はまかりならぬというものである。もっともまだ若い源内は、その条件の重みより、羽ばたく喜びでいっぱいだっただろうが。
晴れて自由の身になった源内が、満を持して開催したのが第5回薬品会「東都薬品会」である。これは当時としては画期的な規模の物産展で、ほとんど日本初の博覧会と呼んでよいものだった。
この薬品会を開催させた背景には、源内の日ごろからの思いがあった。それは高価な輸入品を、安く国産で入手できないかということだった。
自然豊かな日本には、外国の珍しい物産と同じものか、その代替物が、まだ埋もれているにちがいない。それを発見して、国産化できれば、外国への富の流出が減り、国も豊かになる。この国益という考え方は最後まで彼の行動原理となった。
そのために、まずは全国各地からできるだけ多くの物産を集めることが必要と考えたのである。
彼は引札と呼ばれるチラシを全国に配り、18国25箇所に物品の取次所を開設した。物品は江戸へ運賃着払いで送ればよく、早期の返還を確約するなど細部にもアイデアが満載されていた。これによって、従来の2倍近い1300余りの物産を一挙に集めることができたのである。
博覧会後は、薬品会の研究成果を収めた全6巻の『物類品隲(しつ)』を発刊し、本草家・平賀源内の名声をさらに高めた。
源内の本草学の知識と国産への思いは、科学的業績にも結びついていった。そのひとつが「芒消」の製造である。
芒消とは硫酸ナトリウムのことで、現在ではさまざまな工業用途に利用されているが、当時は漢方の下剤・利尿剤として重宝がられていた。しかし輸入にたよっていたため、高価で、容易に手を出せなかった。源内は伊豆産の芒消とその原料を入手し、これを国産化しようと思い立った。
幕府の御用として伊豆に赴いた源内は、芒消の製造に成功したが、産業として成り立たせるまでにはいたらなかった。すぐに飛びつくが飽きるのも早い源内の頭は、このときすでに次のアイデアでいっぱいになっていた。

源内が使っていた薬研 (財)平賀源内先生顕彰会所蔵
|